Entryエントリーフォーム
この度は弊社の採用ページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
下記フォームにご入力の上ご応募ください。
3営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

ZoomもSlackもなかった20年前、「Web会議10人同時接続」を日本企業が実現できたワケ
いまやビジネスに必要不可欠なツールとなったWeb会議システム。コロナ禍をきっかけに社会に広く浸透したため、最近になって登場した比較的新しいサービスだと思っている人は多いかもしれない。
だが実は、20年以上も前に日本で誕生した国産Web会議システムがあるのを知っているだろうか。それがジャパンメディアシステムの『LiveOn』だ。
LiveOnがリリースされたのは2004年。ZoomやSlack、Google meetはまだ影も形もなかった時代だ。しかも現在とは比較にならないほど通信環境は悪く、PCのスペックも十分ではない中で、双方向・多人数のリアルタイム通信を実現していたのだから驚かされる。
なぜジャパンメディアシステムは、数々の制約を乗り越えて、この画期的サービスを生み出せたのか。当時から現在に至るまでLiveOnの開発をリードし続けている技術部部長の堀田大輔さんと遠藤 訓さんに、「制約ありき」でもサービス開発を成し遂げるための極意を聞いた。

ジャパンメディアシステム株式会社
技術部 部長
堀田大輔
ソフトウェア受託開発企業2社を経て、2003年にジャパンメディアシステムに入社し、04年の自社開発Web会議システム『LiveOn』のリリースに貢献した。15年に技術部部長に就任後も、現場にこだわるテックリードとして、同社の技術力を支えている

ジャパンメディアシステム株式会社
技術部 部長
遠藤訓
前職のソフトウェア受託開発から自社開発企業のジャパンメディアシステムに2004年に入社。自社プロダクト『LiveOn』の初期から関わり、主にサーバサイドの開発を担当してきた。技術部 課長~副部長を経て24年8月に部長就任後は、技術マネジメントにも尽力している
ジャパンメディアシステムがWeb会議システムの自社開発に着手したのは2000年代初頭のこと。情報通信機器を扱ってきた同社は、新世代のコミュニケーションツールとなる国産プロダクトを自分たちの手で世に送り出したいとの思いで開発をスタートさせた。
それまで企業が遠隔地をつないで会議を行うには、テレビ会議システムと呼ばれるサービスを利用するのが一般的だった。しかし専用のハード機器やネットワーク回線を導入する必要があり、インフラを整備するだけで大きなコストがかかるため、ユーザーは大手企業などごく一部に限られていたと堀田さんは振り返る。

「インターネットの普及と共に、2000年前後から海外勢を中心に、より手軽に利用できるソフトウエア型のコミュニケーションツールを開発しようとする動きが出てきました。この流れに国内でいち早く目をつけたのが当社です。
大掛かりなハードウエアを用意せずとも、誰もが気軽に自分のパソコンから離れた場所にいる人と対話できたら、画期的なイノベーションになる。私たち開発メンバーとしても、今までにないものをつくる面白さを感じると同時に、このプロダクトが社会に広がることでさまざまな変化を生み出せるのではないかとの期待感がありました」(堀田)
ちなみにインターネット通話ソフトの先駆けとされ、先日サービスを終了したSkypeが正式版をリリースしたのが2004年。LiveOnのVer.1も同年のリリースなので、世界的に見てもジャパンメディアシステムの初動がいかに早かったかが分かる。
ただしそれはエンジニアにとって相当に難易度の高いチャレンジでもあった。現在からは想像がつかないかもしれないが、当時は遠隔で音声や映像をやりとりするには高いハードルがいくつもあったからだ。遠藤さんはその頃の状況をこのように解説する。
「インターネット回線については、1990年代に入ってデジタル回線のISDNが普及しましたが、通信速度は最大で128Kbps。1999年にはより通信速度を増したADSLが登場しましたが、下りで実質10Mbps程度と、ホームページを表示するにも時間がかかるレベルでした。
PCは主にWindows98や2000が使われていた時代で、CPUはPentiumⅡやⅢ。現在は8コア以上のマルチコアも珍しくありませんが、当時はシングルコアが主流でした。メモリも少なく、比較的ハイスペックなPCでも64MBほど。“ギガ”ではなく“メガ”ですから、今とは単位からして違います」(遠藤)
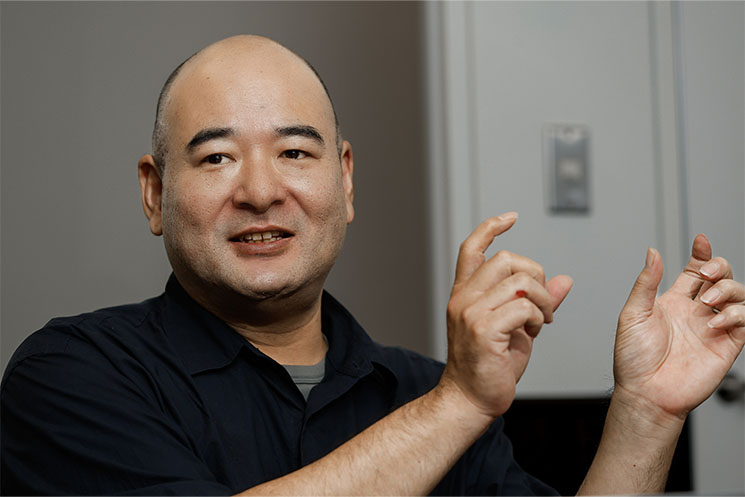
この制約だらけの環境下で音声や映像をやりとりするには、送受信するデータをできるだけ軽くするしかない。そこで初期のSkypeを含めた当時の競合製品は、基本的に1対1で使うツールとして提供されていた。数人で使う場合も、同時に複数が話すと音声の遅延や途切れが発生するため、1人が話し終わってから次の1人が話すといった、交互の発信でなんとか会話のキャッチボールを成り立たせていたという。
だが堀田さんたちは、競合と同じ道を選択しなかった。なんと開発当初から「最大10人が同時利用できるWeb会議システム」を目標に掲げたのだ。
1対1の通話さえ安定しない時代に、無謀ともいえるチャレンジだが、これはサービスを利用するユーザーの目線に立ったからこその判断だった。
「私たちが開発するのはビジネスツールであり、会議利用のニーズに応えるプロダクトです。実際に会議で使おうと思ったら、1人ずつしか話せないなんて不便じゃないですか。実用性を考えれば、双方向で同時に多人数が話せる機能が必須でした。
それに他社ができなかったことを実現すれば、大きな差別化になる。開発者として『10人が同時に使える』という目標は挑戦しがいのある設定でした」(遠藤)
こうして始まった前例のないWeb会議システムの開発。数々の制約がある中でこの目標を実現するため、開発チームがとった戦略は、ユーザーにとって優先度の高い機能や性能に絞り込んで実装することだった。
「最優先としたのは、音声が常にクリアかつリアルタイムで聞こえること。ユーザーにとって、相手の声が途切れたり、聞こえにくかったりするのが、最も大きなストレスになるからです」(堀田)

「一方、会議での利用を想定すると、映像は音声に比べれば優先度が低いと割り切ることに。画面に表示する必要がない映像データはカットするなどして、限られた通信帯域を音声優先で使うことにこだわりました」(堀田)
しかし当時の通信環境では、それでも多人数の音声を安定的に送受信するのは難しい。そこで音声データについても、独自の圧縮技術による軽量化を図る必要があった。
そのために開発チームが選択したのが、「対面で会話するのと全く同じ音質や速度で届けなければいけない」という発想を捨て、「画面越しの会話で違和感がない程度に調整・加工する」という方法だ。
「面と向かって話している時に、相手の口の動きと音声が少しでもズレていたらおかしいと気づきますが、Web会議システムの場合、画面上で見えている映像とのバランスで違和感がなければ気にならない。あくまで優先すべきは、双方向でリアルタイムの会話が成り立つこと。制約が多いからこそ、初期段階ではそこにフォーカスすると割り切りました」(遠藤)

とはいえ、違和感がない程度に音声データを調整すること自体、かなり高度な技術が求められる。簡単にいえば、音声データを抜いたり、足したりして調整するのだが、実際の工程はとてつもなく緻密で気の遠くなるような作業の連続だった。
「通信環境が悪いとサーバに届く音声データが遅れ始め、所々で無音が生じてしまう。そこで無音の箇所に擬似的なダミーデータを足して、ユーザーが聞いて違和感のない音声になるよう調整しました。
またPCのスペックが低いと、処理しきれない音声データがどんどん溜まり、相手の声が遅れて聞こえる。そこで今度はデータの一部を抜くと、再生した時に遅延が発生しません。ただしデータを抜き過ぎると、プツッと途切れたり、早口に聞こえたりして違和感が生じる。だから『5秒間あたり0.001秒ずつ縮めてみよう』といったように、細かい調整を繰り返しました」(堀田)
堀田さんと遠藤さんは口を揃えて「とにかくトライ&エラーの繰り返しだった」と振り返る。だが苦労が多かったはずの当時を語る二人の口調は、どこか楽しそうだ。

「すごく面白かったですよ。前例のない製品なので、いちから自分たちで作るしかない。だからこそエンジニアとしてやりたいことを自由にやれたし、会社も技術的な判断は開発チームに任せてくれた。通信環境やPC環境には制約があっても、開発環境には制約が一切ありませんでした。
それに今と比較すれば、20年前は制約だらけに思えるかもしれませんが、当時はその環境しか存在しなかったのだから、できることをやるしかない。しかもアナログ接続やダイヤルアップ接続の時代に比べれば、通信技術も進化して環境は良くなっているわけです。
つまりどんな時代でも、常にその時が技術的にベストな環境であるはず。だから当時の私たちは、それを制約とすら感じていなかったというのが正直なところです」(遠藤)
こうして2004年にリリースしたLiveOnのVer.1は、「最大10人同時利用」という目標を見事にクリア。さらに翌年リリースしたVer.2では「最大20人同時利用」を可能にした。これは当時のWeb会議システムとしては最多人数で、国内大手電気機器メーカーが提供する競合製品でさえ成し得なかった快挙だった。
その後も技術環境や顧客ニーズの変化に応じてバージョンアップを重ね、現在はCD品質以上の48KHzの高音質と、遅延や途切れのない安定性を兼ね備えた高性能プロダクトへと進化。クラウド型のWeb会議システムが増える中、長年の技術の蓄積を活かしてオンプレミス型にも対応し、現在ではセキュリティーを重視する金融機関や官公庁、自治体にも数多く導入されている。
Web会議システムの黎明期にエンジニアが試行錯誤を繰り返して誕生したプロダクトは、これまでに8500社以上に導入され、市場において確固たる地位を築いている。

現在は通信環境や端末機器のスペックが飛躍的な進化を遂げ、エンジニアが使える技術やリソースも比べ物にならないほど広がっている。
だが堀田さんと遠藤さんは「本当に必要な性能や機能を最優先とし、最小限のリソースでシンプルに作るというスタンスは今も変わらない」と話す。
「あれもこれも使えるからといって、リソースを取捨選択せずに詰め込めば、無駄な機能や過剰な品質につながる。高速・大容量の通信が可能になったとはいえ、余計なものが増えれば動作が遅くなったり、音声や映像が途切れたりして、結局はユーザーのストレスになってしまいます。
何でも使える時代だからこそ、ユーザーが何を求めているのかを理解し、『何を優先するのか?』『必要とされる品質や性能はどのレベルか?』を明確にすることの重要性はますます高まっていると感じます」(遠藤)
ときにはユーザー自身でさえ、自分が求めるものをうまく言語化できていないこともある。だからこそエンジニアは顧客からの要望をそのまま受け取るのではなく、その裏にある本当のニーズを突き詰める思考が必要だ。
「先日もある自治体から『LiveOnを使って議会を録画したい』とご相談を受けたのですが、社内で議論した結果、『そもそもLiveOnを使う必要がない』との結論になったことがあります。
もちろん技術的には可能ですが、お客さまが求めるのが録画とデータ保存だけなら、シンプルな録画専用システムを作った方がコストは抑えられるので、営業を通じてそのようにご提案しました」(堀田)
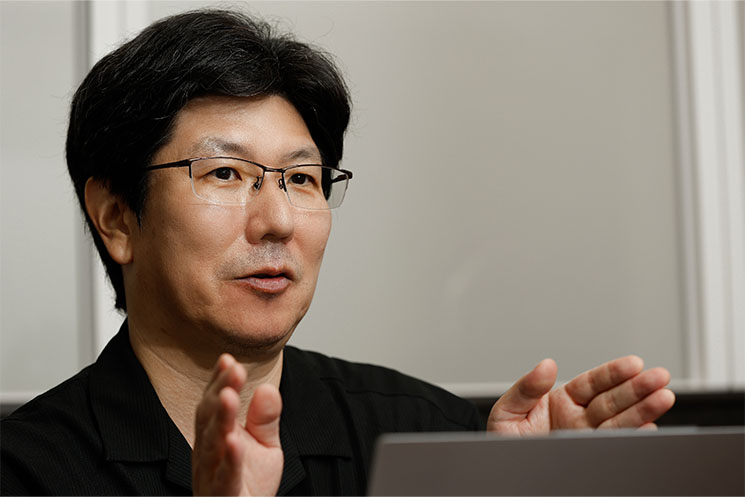
「お客さまの言葉をそのまま実現することが、必ずしもお客さまのためになるとは限らない。だからこそエンジニアは『これは本当に必要なのか?』と問い続ける姿勢が求められます」(堀田)
現在は環境面での制約は少なくなったとはいえ、どんな開発にも予算や納期の制約はついて回るし、会社の方針やクライアントの意向によってやれることが限定される場面も多々ある。制約がゼロの開発などあり得ないからこそ、二人の言葉から学ぶものは多い。
「制約の多い開発は、例えるならDIYみたいなもの。限られた材料や道具しかなくて、周囲からも『そんなもので家具を作るなんて無理でしょ』と言われる中で、思い通りのものを作れたら『やってやったぜ』って感じになる(笑)。制約を乗り越えて得られる達成感こそが、開発の醍醐味だと思っています」(堀田)
「私の場合は、パズルや謎解きのイメージに近いですね。どちらも限られた情報をヒントに、『これとこれを組み合わせたらうまくいくんじゃないか』と創意工夫しながらゴールに辿り着く。特定の条件下で答えを探し出すのは、ワクワクするような面白さがあります」(遠藤)

そして今、LiveOnはさらなる進化を遂げるべく、一大リニューアルを予定している。これまでに培った技術やノウハウを活かしつつ、開発言語の変更やIPv6への対応などによるリファクタリングを行う計画だ。
「20年前に私たちが経験した『制約の中で新しいものをつくる』という面白い体験がまたできる。当時を知らない若手エンジニアと共に、あの楽しさを再び味わえることを私たちも楽しみにしています」(遠藤)
オンライン会議がすっかり当たり前になり、選択肢も増えた今だからこそ、二人は「最初に挑戦した強みを活かして、これからも“本当に必要なもの”を届けていきたい」と語ってくれた。制約だらけの中で壁を突破し続けてきたLiveOnは、これからも“メイド・イン・ジャパン”らしい丁寧さと技術力を武器に、力強く走り続ける。
この度は弊社の採用ページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
下記フォームにご入力の上ご応募ください。
3営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。